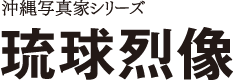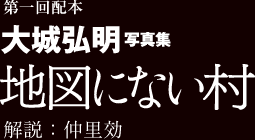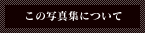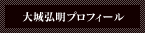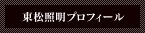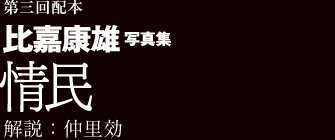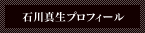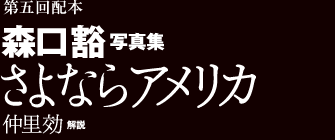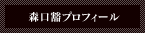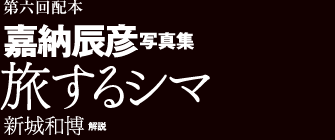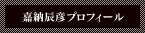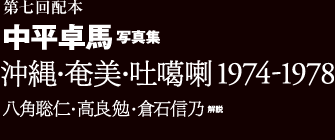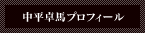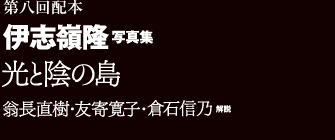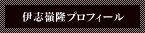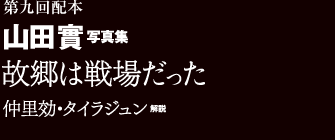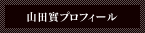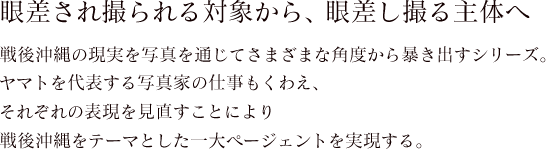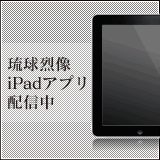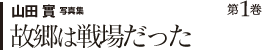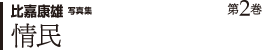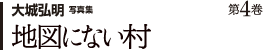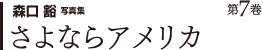- 大城弘明(おおしろ・ひろあき)
- 1950年、沖縄県三和村福地(現糸満市)生まれ。1968年、琉球大学入学。民俗研究クラブ、写真クラブで活動。沖縄の復帰闘争、全軍労運動、米軍基地、沖縄戦の跡などを撮影。1972年、琉球大学卒業。フリーカメラマン、岩波映画写真部契約撮影助手として活動。1973年、沖縄タイムス写真部に入社。2010年3月、沖縄タイムス写真部を定年退職。同年4月から同部嘱託。
- 主な写真展
- 個展「生まれ島福地」(1976年、写真ひろば「あーまん」)、個展「大山・マーシー」(1977年、写真ひろば「あーまん」)、「こだわりの眼 写真で考える沖縄戦後史展」に「白地に赤く」出品(1992年、県内5市移動展)、「戦後50年沖縄 写真ひろば『あーまん』連続写真展」に「地図にない村・三和村」出品(1995年、県民ギャラリー)、「カジマーイ12人の眼」に出品(1999年、那覇市民ギャラリー)、「琉球烈像――写真で見るオキナワ」に出品(2002年、那覇市民ギャラリー)、「六月の記憶」に「地図にない村」出品(2006年、糸満市役所ギャラリー)、個展「地図にない村」(2009年、糸満市役所ギャラリー)、個展「地図にない村」(2010年、県民ギャラリー)
共著に「沖縄島唄紀行」(2001年、小学館)
- 東松照明(とうまつ・しょうめい)
- 1930年、愛知県名古屋市生まれ。1954年、愛知大学法経済学部卒業。岩波写真文庫スタッフとして岩波書店入社(56年退社)。1958年、第1回日本写真批評家協会新人賞受賞。1959年、奈良原一高らとセルフエージェンシーVIVO設立(61年解散)。1961年、土門拳らとの共著『hiroshima-nagasaki document 1961』(原水爆禁止日本協議会)で第5回日本写真批評家協会作家賞受賞。1966年より73年まで、東京造形大学映像科助教授。1975年、『太陽の鉛筆――沖縄・海と空と島と人びと・そして東南アジアへ』(毎日新聞社)で日本写真家協会年度賞受賞。76年、同書で第17回毎日芸術賞、第26回芸術選奨文部大臣賞受賞。1995年、紫綬褒章受章。2003年、第56回中日文化賞受賞。2004年、日本写真協会功労賞受賞。
- 主な写真集など
- 『〈11時02分〉NAGASAKI』(1966年、写真同人社)、『日本』(1967年、写研)、『サラーム・アレイコム』(1968年、写研)、『OKINAWA 沖縄OKINAWA』(1969年、写研)、『おお! 新宿』(1969年、写研)、『戦後派』(1971年、中央公論社)、『I am a king』(1972年、写真評論社)、『太陽の鉛筆――沖縄・海と空と島と人びと・そして東南アジアへ』(1975年、毎日新聞社)、『泥の王国』(1978年、朝日ソノラマ)、『光る風――沖縄』(1979年、集英社)、『昭和写真・全仕事15 東松照明』(1984年、朝日新聞社)、『廃園』(1987年、PARCO出版)、『さくら・桜・サクラ120』(1990年、ブレーンセンター)、『さくら・桜・サクラ66』(1990年、ブレーンセンター)、『時の島々』(1998年、岩波書店)、『VISIONS of Japan TOMATSU Shomei』(1998年、光琳社出版)、『日本の写真家30 東松照明』(1999年、岩波書店)、『東松照明 1951-60』(2000年、作品社)、Sandra S. Phillips, Leo Rubinfien, andJohn W. Dower, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation (San Francisco: SanFrancisco Museum of Modern Art, 2004)
- 主な写真展
- 「いま!! 東松照明の世界・展」(1981-84年、全国30か所巡回)、「SHOMEITOMATSU Japan 1952-1981」(1984-86年、フォルム・シュタットパルク、グラーツほかオーストリア、西ドイツ巡回)、「東松照明写真展 インターフェイス」(1996年、東京国立近代美術館)、「日本列島クロニクル――東松照明の50年」(1999年、東京都写真美術館)、「東松照明展 長崎マンダラ」(2000年、長崎県立美術博物館)、「東松照明展 沖縄マンダラ」(2002年、浦添市美術館)、「愛知曼陀羅―東松照明の原風景―」展(2006年、愛知県美術館)、「東松照明の写真 1972-2002」展(2003年、京都国立近代美術館)、「Shomeitomatsu: Skin of the Nation」(2004-2007年、サンフランシスコ近代美術館ほかアメリカ、ヨーロッパ巡回)、「東松照明[Tokyo曼陀羅]」展(2007年、東京都写真美術館)、「東松照明展―色相と肌触り 長崎―」(2009年、長崎県美術館)、「東松照明 時を削る展」(2010年、長崎県美術館)
- 東松照明(とうまつ・しょうめい)
- 1930年、愛知県名古屋市生まれ。1954年、愛知大学法経済学部卒業。岩波写真文庫スタッフとして岩波書店入社(56年退社)。1958年、第1回日本写真批評家協会新人賞受賞。1959年、奈良原一高らとセルフエージェンシーVIVO設立(61年解散)。1961年、土門拳らとの共著『hiroshima-nagasaki document 1961』(原水爆禁止日本協議会)で第5回日本写真批評家協会作家賞受賞。1966年より73年まで、東京造形大学映像科助教授。1975年、『太陽の鉛筆――沖縄・海と空と島と人びと・そして東南アジアへ』(毎日新聞社)で日本写真家協会年度賞受賞。76年、同書で第17回毎日芸術賞、第26回芸術選奨文部大臣賞受賞。1995年、紫綬褒章受章。2003年、第56回中日文化賞受賞。2004年、日本写真協会功労賞受賞。
- 主な写真集など
- 『〈11時02分〉NAGASAKI』(1966年、写真同人社)、『日本』(1967年、写研)、『サラーム・アレイコム』(1968年、写研)、『OKINAWA 沖縄OKINAWA』(1969年、写研)、『おお! 新宿』(1969年、写研)、『戦後派』(1971年、中央公論社)、『I am a king』(1972年、写真評論社)、『太陽の鉛筆――沖縄・海と空と島と人びと・そして東南アジアへ』(1975年、毎日新聞社)、『泥の王国』(1978年、朝日ソノラマ)、『光る風――沖縄』(1979年、集英社)、『昭和写真・全仕事15 東松照明』(1984年、朝日新聞社)、『廃園』(1987年、PARCO出版)、『さくら・桜・サクラ120』(1990年、ブレーンセンター)、『さくら・桜・サクラ66』(1990年、ブレーンセンター)、『時の島々』(1998年、岩波書店)、『VISIONS of Japan TOMATSU Shomei』(1998年、光琳社出版)、『日本の写真家30 東松照明』(1999年、岩波書店)、『東松照明 1951-60』(2000年、作品社)、Sandra S. Phillips, Leo Rubinfien, andJohn W. Dower, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation (San Francisco: SanFrancisco Museum of Modern Art, 2004)
- 主な写真展
- 「いま!! 東松照明の世界・展」(1981-84年、全国30か所巡回)、「SHOMEITOMATSU Japan 1952-1981」(1984-86年、フォルム・シュタットパルク、グラーツほかオーストリア、西ドイツ巡回)、「東松照明写真展 インターフェイス」(1996年、東京国立近代美術館)、「日本列島クロニクル――東松照明の50年」(1999年、東京都写真美術館)、「東松照明展 長崎マンダラ」(2000年、長崎県立美術博物館)、「東松照明展 沖縄マンダラ」(2002年、浦添市美術館)、「愛知曼陀羅―東松照明の原風景―」展(2006年、愛知県美術館)、「東松照明の写真 1972-2002」展(2003年、京都国立近代美術館)、「Shomeitomatsu: Skin of the Nation」(2004-2007年、サンフランシスコ近代美術館ほかアメリカ、ヨーロッパ巡回)、「東松照明[Tokyo曼陀羅]」展(2007年、東京都写真美術館)、「東松照明展―色相と肌触り 長崎―」(2009年、長崎県美術館)、「東松照明 時を削る展」(2010年、長崎県美術館)
- 石川真生(いしかわ・まお)
- 写真家
1953年生、沖縄県生まれ、豊見城市在住。 - 主な展示会
- 1977年、「金武の女たち」(東京都、ミノルタフォトスペース)
1987年、「LIFE IN PHILLY」(東京都、ミノルタフォトスペース)
1999年、「日の丸を視る目」(大阪府松原市の阪南中央病院をかわきりに2000年まで全国各地で巡回展)
2003年、「KEEP IN TOUCH: POSITIONS IN JAPANESE PHOTOGRAPHY」カメラ・オーストリア特別企画展に参加出展。(オーストリア、グラーツ市美術館内、カメラ・オーストリアギャラリー)
2004年、「沖縄ソウル」(神奈川県横浜市、横浜美術館で企画展「ノンセクト・ラディカル 現代の写真III」に参加)
2004年10月、「沖縄ソウル」(アメリカ・ニューヨーク州、PS1コンテンポラリーアートセンター・アメリカ近代美術別館の企画展「永続する瞬間―沖縄と韓国、内なる光景」に参加出品)
2009年、「フェンス OKINAWA」(沖縄県那覇市主催、那覇市民ギャラリー)
2010年、「セルフポートレイト<携帯日記>」/「日の丸を視る目」(東京都、TOKIO OUT Of PLACE) - 主な著書
- 『熱き日々 in キャンプハンセン!!』(比嘉豊光との共著、あーまん企画、1982年)
『フィリピン』(自費出版、1989年)
『港町エレジー』(自費出版、1990年)
『仲田幸子一行物語』(自費出版、1991年)
『沖縄と自衛隊』(高文研、1995年)
『これが沖縄の米軍だ』(國吉和夫・長元朝浩との共著、高文研、1996年)
『沖縄海上ヘリ基地』(高文研、1998年)
『沖縄ソウル』(太田出版、2002年)
『シマが揺れる』(浦島悦子との共著、高文研、2006年)
『LIFE IN PHILLY』(Gallery OUT of PLACE 、ZEN FOTO Gallery、2010年) - Ishikawa, Mao
- Photographer
b. 1953 in Okinawa
Resides in Tomigusuku-city, Okinawa - Selected Exhibitions
- 1977
"Women of Kin-town", Minolta Photo Space, Tokyo
1987
"LIFE IN PHILLY", Minolta Photo Space, Tokyo
1999-2000
"Eye Grazing at Hinomaru, the Japanese National Flag", at various galleries throughout Japan
2003
"KEEP IN TOUCH: POSITIONS IN JAPANESE PHOTOGRAPHY", in the Kamera Austria gallery special exhibition, Graz Art Museum, Graz, Austria
2004
"Okinawa Soul", in "Non-sector Radical Contemporary Photography III", Yokohama Museum of Art, Kanagawa, Japan
"Okinawa Soul", in "The Perpetual Moment: Visions within Okinawa and South Korea", PS1 Contemporary Art Center, New York
2009
"Fences, Okinawa", Naha Citizen's Gallery, Okinawa
2010
"Self-portrait: Camera Phone Diary", and "Eyes Grazing at Hinomaru, the Japanese National Flag", TOKIO OUT OF PLACE. Tokyo - Publications
- Atsuki Hibi in Camp Hansen (Hot Days in Camp Hansen), collection of photographs in collaboration with Higa, Toyomitsu, Aman Kikaku, 1982
The Philippines, collection of photographs, private publication, 1989
Minatomachi Eregii, (A Port Town Elegy), collection of photographs, private publication, 1990
Naka Sachiko Ikko Monogatari, (A Story of Sachiko Nakada's Theater Company), collection of photographs, private publication, 1991
Okinawa to Jieitai, (Okinawa and Japan's Self Defence Forces), photographs and essays, Kobunken, 1995
Kore ga Okinawa no Beigun Da, (This is the US Military in Okinawa), photographs, in collaboration with Kuniyoshi, Kazuo and Nagamoto, Tomohiro, Kobunken, 1996
Okinawa Kaijo Heri Kichi, (US Marines Coprs Helicopter Base over Okinawa's Sea), photographs and essays, Kobunken, 1998
Okinawa Souru, (Okinawa Soul), autobiography with photographs, Ota Shuppan, 2002
Shima ga Yureru, (Our Community Is Shaken), photographs, in collaboration with Urashima Etuko, Kobunken, 2006
LIFE IN PHILLY, Gallery OUT of PLACE/ ZEN FOTO GALLERY, 2010
- 森口豁(もりぐち・かつ)
-
1937年、東京生まれ。
1958年、玉川大学文学部中退。琉球新報社入社、東京支社報道部記者に。
1959年、琉球新報社会部記者として米軍政下の沖縄に移住。(61年より日本テレビ沖縄通信員を兼務)
1963年、琉球新報社退職。日本テレビ「沖縄特派員」に。
1974年、日本テレビ本社に転勤、報道部記者を経て、77年より報道番組ディレクターに。
1987年、ドキュメンタリー番組『ひめゆり戦史・いま問う国家と教育』『島分け・沖縄鳩間島哀史』など一連の沖縄作品でテレビ大賞優秀個人賞、JCJ(日本ジャーナリスト会議)奨励賞を受賞。
1990年、日本テレビ退職、フリージャーナリストに。「沖縄を語る一人の会」主宰。
2005年、著書『だれも沖縄を知らない――27の島の物語』で第26回沖縄タイムス出版文化賞受賞。 - 主な著書
-
『写真と権力――沖縄・フィルム押収事件闘争記録』(共著、1975年、アディン書房)
『ミーニシ吹く島から――極私的沖縄論』(1980年、アディン書房)
『子乞い――八重山・鳩間島生活誌』(1985年、マルジュ社)
『旅農民のうた――裏石垣開拓小史』(1985年、マルジュ社)
『沖縄こころの軌跡――1958~1987』(1987年、マルジュ社)
『復帰願望 昭和の中のオキナワ――森口豁ドキュメンタリー作品集』(1992年、海風社)
『最後の学徒兵――BC級死刑囚 田口泰正の悲劇』(1993年、講談社/96年、講談社文庫)
『ヤマト嫌い――沖縄言論人 池宮城秀意の反骨』(1995年、講談社)
『反骨のジャーナリスト――池宮城秀意セレクション』(共著、1996年、ニライ社)
『代理署名裁判――沖縄県知事証言』(共著、1996年、ニライ社)
『「安保」が人をひき殺す――日米地位協定=沖縄からの告発』(1996年、高文研)
『沖縄 近い昔の旅――非武の島の記憶』(1999年、凱風社)
『沖縄 元気力』(共著、2001年、東京書籍)
『だれも沖縄を知らない――27の島の物語』(2005年、筑摩書房)
『米軍政下の沖縄――アメリカ世の記憶』(2010年、高文研) - 主な写真展など
-
2003年、「山形国際ドキュメンタリー映画祭」参加。
2004年、沖縄映画祭「琉球電影列伝 境界のワンダーランド」参加。
2008年、「沖縄・プリズム 1872~2008」にドキュメンタリー「沖縄の十八歳」「一幕一場・沖縄人類館」出品。(東京・国立近代美術館)
2010年、日米安保改訂50年企画「さよならアメリカ 森口豁展」(沖縄・画廊沖縄)
2010年、「米軍政下の沖縄 アメリカ世の記憶 森口豁写真展」(沖縄・ちゃたんニライセンター)
- 嘉納辰彦(かのう・たつひこ)
-
1952年 沖縄県那覇市生まれ
東京写真専門学院卒業
1976年 写真ひろば「あーまん」設立参加
10月 個展(あーまん)
1979年 「今日の写真・展」出品(神奈川県民ギャラリー)
「視覚の現在'79写真展」出品(那覇市・ダイナハ)
沖縄県芸術祭・写真部門で県教育長賞受賞(「17才」)
10月 個展(あーまん)
1980年 個展(東京・新宿PUT)
1981年 沖縄県芸術祭・写真部門で県知事賞受賞(「拝所」)
1982年 2月 個展「島からの風」(那覇市・クラフト国吉ギャラリー)
1985年 「写真15人展」出品(那覇市・県民アートギャラリー)
同人写真誌「美風」発刊
1986年 個展「島からの風」(沖縄三越ギャラリー)
1988年 グループ展「美風・展」出品(那覇市・県民アートギャラリー)
1990年 7月 個展「南米のウチナーンチュ」(市民ギャラリー)
1992年 「写真で考える沖縄戦後史」出品(市民ギャラリー)
1995年 3月 個展「もうひとつのウチナー」(市民ギャラリー)
1995年 5月 個展「島からの風」(名古屋・セントラルギャラリー)
1996年 5月 個展「もうひとつのウチナー」(名古屋・セントラルギャラリー)
1997年 写真展「カジマーイ12人の眼」出品(市民ギャラリー)
2002年 写真展「琉球烈像――写真で見るオキナワ」出品(市民ギャラリー)
「おきなわの祭り」出品(東京・吉祥寺伊勢丹)
2003年 10月 山形国際ドキュメンタリー映画祭関連イベント「太陽の果実 沖縄写真ラプソディ」出品
2007-8年 「キューバのウチナーンチュと今日のキューバ」(石川歴史民俗資料館、名護博物館、本部町立博物館、糸満市市民ギャラリー、豊見城市役所、おきなわ時間美術館)
2009年 写真集『クーバミスタ アジマー』(沖縄キューバ友好協会)刊行
2010年 写真集『もうひとつのウチナー』(ボーダーインク)刊行
- 中平卓馬(なかひら・たくま)
-
1938年 東京・原宿に生まれる。
1963年 東京外国語大学スペイン科卒業。現代評論社「現代の眼」編集部に勤務(65年退職)。
1968年 多木浩二、高梨豊、岡田隆彦と写真同人誌「プロヴォーク」創刊(2号より森山大道が参加、70年解散)。
1969年 第6回パリ青年ビエンナーレに出品。
第13回日本写真批評家協会賞新人賞受賞。
1970年 『まずたしからしさの世界をすてろ――写真と言語の思想』(多木浩二ほかと共著、田畑書店)
写真集『来たるべき言葉のために』(風土社/再刊、オシリス、2010年)
1971年 第7回パリ青年ビエンナーレに出品。
1973年 『なぜ、植物図鑑か――中平卓馬映像論集』(晶文社/ちくま学芸文庫、2004年)
1974年 「写真のための写真」展(東京・シミズ画廊)に出品。
「15人の写真家」展(東京国立近代美術館)に出品。
1976年 「travaux/débat/projection: l'avant-garde au Japon」(マルセイユ・ADDA画廊)に出品。
1977年 『決闘写真論』(篠山紀信と共著、朝日新聞社/朝日文庫、1995年)
1983年 写真集『新たなる凝視』(晶文社)
1989年 写真集『Adieu à X』(河出書房新社。同書で1990年に第2回「写真の会」賞受賞/新装版、2006年)
個展「あばよX」(東京・FOTO DAIDO)
「11人の1965~75――日本の写真は変えられたか」展(山口県立美術館)に出品。
1997年 個展「日常――中平卓馬の現在」(名古屋・中京大学アートギャラリー C・スクエア)
1999年 写真集『日本の写真家36 中平卓馬』(岩波書店)
2002年 写真集『hysteric Six NAKAHIRA Takuma』(Hysteric Glamour)
「フォトネシア/光の記憶・時の果実――復帰30年の波動」展(那覇市民ギャラリー)に出品。
2003年 個展「中平卓馬展 原点復帰―横浜」(横浜美術館/那覇市民ギャラリーに巡回)
2004年 個展「なぜ、他ならぬ人間=動物図鑑か??」(東京・ShugoArts)
「Spread in Prato 2004」(イタリア・プラトー)に出品。
2005年 「Chikaku: Time and Memory in Japan」(オーストリア・グラーツ美術館/スペイン/ビーゴ現代美術館、川崎市岡本太郎美術館に巡回)
「MEGANEURA」展(八戸市美術館)に出品。
2007年 個展「なぜ、他ならぬ横浜図鑑か!!」(ShugoArts)
『見続ける涯に火が…批評集成1965-1977』(八角聡仁、石塚雅人編、オシリス)
2011年 個展「Documentary」(東京・BLD GALLERY、ShugoArts)
写真集『Documentary』(Akio Nagasawa Publishing)
『都市 風景 図鑑』(月曜社)
個展「キリカエ」(大阪・Six/ソウル・Sixに巡回)
- 伊志嶺隆(いしみね・たかし)
-
1945年 台湾に生まれる
1968年 東京写真専門学校入学(中途退学)
1988年 「アサヒカメラ」9月号(朝日新聞社)に「光と陰の島」掲載
個展「光と陰の島」(東京・銀座ニコンサロン/沖縄・石垣市民会館、那覇市民ギャラリーを巡回)
1990年 個展「72年の夏」(沖縄・那覇市民ギャラリー)
「FOTOFEST '90」(アメリカ・テキサス州ヒューストン)出品
1991年 「第34回新象展」入選
「1991年度朝日広告賞」一般公募の部入選
1992年 「こだわりの眼 写真で考える沖縄戦後史展」(沖縄市、名護市、石垣市、平良市を巡回)出品
『こだわりの眼 写真で考える沖縄戦後史』(沖縄タイムス社)に掲載
「Estaminet」2月号(ぎょうせい)に「南風の海人」掲載
1993年 3月28日、逝去(享年47歳)
「オキナワ展 復帰20周年 その歩みと文化」(神奈川・川崎市民ミュージアム)出品
「伊志嶺隆遺作展」(東京・モール)
『伊志嶺隆遺作集 光と陰の島』(伊志嶺隆の会)刊行
1994年 「伊志嶺隆遺作展」(沖縄・那覇市民ギャラリー)
『伊志嶺隆遺作集』(伊志嶺隆遺作集実行委員会)刊行
2007年 「沖縄文化の軌跡1872-2007」(沖縄県立博物館・美術館)
2008年 「沖縄・プリズム1872-2008」(東京国立近代美術館)
2011年 伊志嶺隆写真展「島の陰、光の海」(沖縄・那覇市民ギャラリー)
パブリックコレクション 那覇市歴史博物館
- 山田 實(やまだ・みのる)
-
1918年 那覇市東町に生まれる
1936年 沖縄県立二中卒業。在学中は絵画サークル「緑樹会」に所属するが、トーゴーカメラで撮影もはじめる
1941年 明治大学専門部商科卒業。同年、同大学新聞高等研究科(二部)卒業。在学中は大学新聞編集委員。日産土木株式会社入社と同時に満州に赴任
1944年 金州で現地召集、関東軍入隊
1945年 北満州で終戦、シベリアに抑留
1947年 舞鶴へ帰還
1952年 沖縄へ帰還、山田写真機店を桜坂に開業(71年に国際通に、94年に現在の久米町に移転)、72年の本土復帰までニコン琉球総代理店。沖縄最初の写真サークル「沖縄写真クラブ」へもかかわる
1956年 琉球新報社主催のコンクールで「光と影」が特選、写真家として注目される
1958年 二科会沖縄支部結成メンバーとなる
1959年 「沖縄ニッコールクラブ」結成(会長就任)
1962年 沖展会員となる。濱谷浩の取材に同行、写真テクニックや写真観に強い影響を受ける
1966年 沖縄写真連盟設立メンバーとなる(72年に会長)。水島源晃、親泊康哲、当真荘平、安谷屋正義らとともに「現代写真家・五人展」(沖縄タイムスホール)、画家の安谷屋正義と共同制作。沖展選考委員となる
1967年 水島源晃、親泊康哲、当真荘平らとともに沖縄で初の野外展「写真四人野外展」(琉球政府中庭)
1969年 東松照明の来沖で身元引受人。ほかに林忠彦、木村伊兵衛、岩宮武二の身元引受人を務める
1971年 第1回写真展(沖縄タイムスホール)、山田實写真小品展(沖縄物産センター画廊)
1972年 沖縄県写真機材商組合長として、カメラ販売、普及に力をいれる。本土復帰に伴い、「沖縄ニッコールクラブ」は「ニッコールクラブ沖縄支部」に改称(支部長就任)
1974年 「東松照明・沖縄ワークショップ」の窓口となる
1977年 第2回写真展(沖縄タイムスホール)。沖縄タイムス芸術選賞大賞受賞
1978年 平良正一郎と「カナダ写真展」(沖縄タイムスホール)
1979年 県芸術祭(第8回)に新設された写真部門で水島源晃、親泊康哲、比嘉康雄、平良孝七とともに実行委員を務める
1990年 第4回写真展(那覇市民ギャラリー)
1994年 第6回写真展(那覇市民ギャラリー)
1995年 第7回写真展(那覇市民ギャラリー)
1999年 第8回写真展(那覇市民ギャラリー)
2000年 沖縄県文化功労者
2002年 写真集『子どもたちのオキナワ 1955-1965』刊行(池宮商会)、地域文化功労者、沖縄県文化協会賞受賞
2003年 第9回写真展「時の謡、人の譜、街の紋」(那覇市民ギャラリー)
2009年 琉球新報賞受賞
2012年 『山田實が見た戦後沖縄』刊行(琉球新報社)、写真展「人と時の往来─写真でつづるオキナワ」(沖縄県立博物館・美術館)
パブリックコレクション 沖縄県立美術館